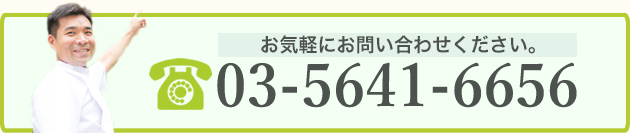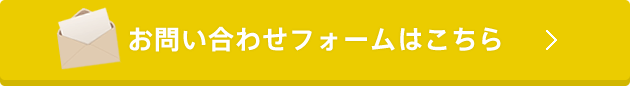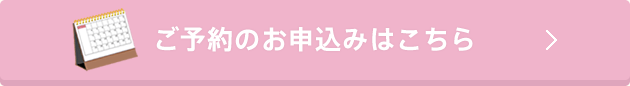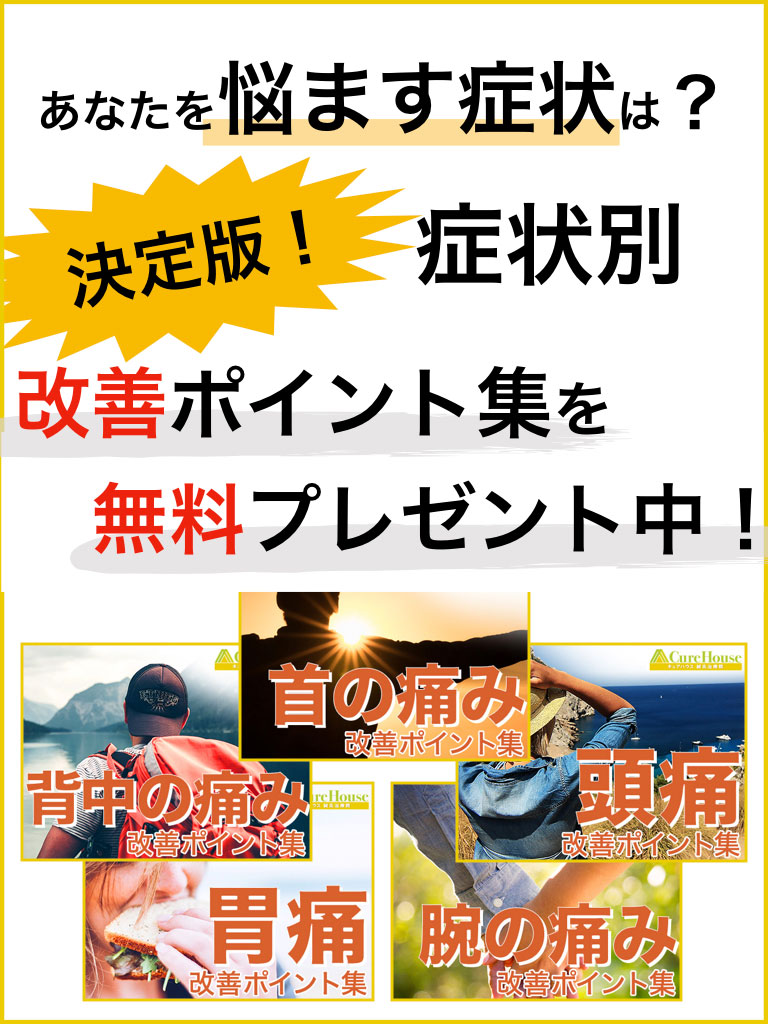入眠障害を引き起こす9つの原因
 キュアハウス院長 中村幸生
キュアハウス院長 中村幸生

入眠障害という寝つきが悪い問題で悩まれている人がいます。
なぜ眠れないのかを理解している人と理解できていない人がいます。
ここでは、入眠障害の原因について考えていくことにしましょう。
ちなみに、睡眠全般の質を高める方法については、こちらを参照してみてください。
入眠障害とは、文字通り、睡眠に入りにくい状態を表します。
最も不眠症を実感する睡眠障害の一つといえるでしょう。
いろいろな協会や学会で定義づけをしていますが、大事なことは、
『これまでの睡眠とは違って入眠しにくくなっている』
ということです。
これまでは、10時に眠くなり、入眠できたのに、最近は、10時にお布団の中に入っても、入眠できず、気づいたら12時を回っていたなんてことが起き始めたら、入眠障害になりつつあるわけです。
ここで入眠障害に気づければ、【早期発見】です。
この段階で、入眠の問題を改善できれば大事にならずに済みます。
ところが、このような段階では、多くの場合、『明日は寝れるだろう』何て軽く思ってしまうわけです。
もちろん、明日は速やかに入眠できれば何の問題もありません。
けれど、明日は?明後日は?もっともっと長くいつまで経っても眠れなくなってしまう事って普通に起こるわけです。
なぜなら、1日だけ入眠できなかったという場合には、その日の生活の中でたまたま入眠できない理由があっただけで体質化していないのですから。
問題は、何日も、何か月も、何年も同じように入眠できない完全なる入眠障害になってしまった場合です。
このような場合には、確実にあなたが入眠できないような身体を作るための生活をしているということになるのです。
要するに、入眠障害で苦しんでいる原因はあなたが握っているということになるわけです。
とはいっても、入眠障害を生みだすために生活をしているわけではないと思いますし、入眠障害の影響で疲れが抜けないからと疲労回復のために行っている行動が、入眠障害の原因となっていることもあるわけです。
そういうことから、日常生活に潜む入眠障害の原因となりうる問題についてお話していくことにしましょう。
1.二度寝が入眠障害の原因と対処法

入眠障害が原因でまともに寝た気がしないと、朝目が覚めても、二度、三度といつまでも寝てしまう人がいます。
また、入眠障害だけでなく、中途覚醒というもう一つの睡眠障害を併発していると、入眠しにくいだけでなく、やっと寝れても1~2時間でまた目が覚めてしまうなんてことも起きてしまいます。
すると、意地でも寝ようと努力をし始めます。
この結果、より入眠障害を悪化させるための行動になってしまうことがあるのです。
なぜなら、本来、睡眠中は副交感神経が働くことになっているからです。
ところが、途中で目が覚めたり、早く目が覚めたりしたその瞬間には、交感神経が動いています。
交感神経は活動用の神経ですので、交感神経が働き始めたら動き出さなければなりません。
ところが、本人は、意地でも寝ようとするわけです。
この『意地で』ということがさらに交感神経に拍車をかけ、入眠しにくくさせてしまうのです。
副交感神経を働かせたいのであれば、ゆっくりと穏やかな状態になっておくことが重要なのですが、この状態ですら努力で作ろうとすると強制力が働き、交感神経の活動となってしまいます。
できれば、入眠障害で苦しんでいる場合には、目が覚めたら、諦めて起きることをしてみてください。
すると、その日一日は眠い状態での活動となりますが、その状態が今度の睡眠の寝つきを良くしてくれるきっかけとなってくれます。
2.昼寝が入眠障害の原因と対処法

入眠障害が原因で、日中に眠気に襲われることがあります。
従って、昼寝やうたた寝をついついしてしまうと思います。
この気持ちは痛いほど理解できるのですが、睡眠とは違うタイミングで寝てしまうと、さらに入眠しにくい状態を作ってしまいますので、そこはあえて我慢して、何か行動に移す努力をしましょう。
昼間の眠気に耐えれば耐えるほど入眠しやすくなります。
3.コーヒーによる入眠障害の原因と対処法

日中の眠気を我慢するために覚醒作用のあるコーヒーで活性化させようとする人がいます。
コーヒーは眠気に打ち勝つための飲み物でもありますので、飲みすぎてしまうと、睡眠に影響が出ることが多いのです。
意外なことに、不眠症で悩まれている多くの人がコーヒーの愛好家であったりするのです。
コーヒーの覚醒作用を抑えてしまうと、昼間の眠気を抑えられないので、飲む意味がなくなります。
眠気を抑えるためにコーヒーを飲んでいるのであれば、入眠できなくても仕方ないと言えます。
入眠障害が原因で、眠気に襲われ、コーヒーで回避しているのであれば、いつまでもこの負の連鎖は続いてしまいます。
そこで、コーヒーが好きで飲みたいのであれば、朝食や昼食直後だけにしてみたらいかがでしょうか?
入眠障害がない場合には、おやつの時も飲んでいいのですが、入眠障害があるにもかかわらず、おやつの時間にもコーヒーを飲んでしまえば、入眠障害を治すどころか、悪化させてしまう可能性が高くなります。
できるだけ日中の眠気は動いてごまかし、できる限り早く入眠障害を克服できるようになりましょう。
4.マッサージによる入眠障害の原因と対処法

入眠障害が原因で肩や首が苦しくなることがあります。
いわゆる肩こりや首こりですね。
このようなコリを感じるとさらに入眠しにくくなります。
そこで、多くの場合、マッサージや整体に通い、少しでも疲れを取り除き、あわよくば、入眠しやすくなったらラッキー的な感じで、通い始めるわけです。
ところが、マッサージをしてもらった筋肉は徐々に固さが強調されていきます。
揉んでも揉んでも固くなっていくのです。
もしくは、整体で首や背中をボキボキやってもらうと、その場は、スッキリした感じになります。
ところが、何度も首や背中をボキボキしている間に、これまでなかった痛みに襲われてしまい、より入眠しにくくなり、睡眠の質自体が低下し完全なる入眠障害に陥る危険性さえあるのです。
このようなことから、入眠障害が原因で疲れたりこっている身体をマッサージや整体で改善を図るのではなく、一日も早く入眠障害の原因を理解して、速やかに入眠できるようにすることで、無駄な苦しみを増やさないようにしましょう。
5.薬で入眠障害を抜け出すのは危険

入眠障害を病院で治してもらおうと思う人は多いですが、実は、この選択はかなり危険です。
なぜなら、医師は、睡眠薬を利用することに慣れ過ぎているからです。
大きな病院で勤めると、夜間診療も請け負わなければなりません。
医師も看護師も、夜勤があれば、昼間に睡眠を取るしか疲れを取り除く方法がありません。
かといって、明るく、気温も高く、騒がしい日中に眠ることは、かなり困難を極めます。
そこで、利用するのが睡眠薬。
そうやって若い頃忙しい日々を乗り切っているので、何の嫌悪感もなく患者さんに出す癖があります。
けれど、入眠障害で悩んでいるあなたは、夜勤をしているわけではないですよね?
夜勤と日勤が日々入れ替わるような勤務体系であれば、それは仕方ありませんので、薬に頼るのも一つの手段になります。
でも、そういう勤務体系ではなく、日中に活動し、夜間は睡眠を取ることが可能であれば、薬に頼ることよりも、速やかに入眠できる状態を作り上げることの方が重要なのです。
なぜなら、薬で寝ている以上、ちゃんとした睡眠が取れないからです。
一度でも薬を使って寝たことがあれば、理解できると思いますが、決して薬で寝て、スッキリ目覚めることはありません。
これは、睡眠薬からの目覚めは、若干、『完全に薬の効能が切れたわけではない』という状態だからスッキリ目覚めていないのです。
6.近代化が入眠障害の原因

現代社会は、科学の進歩と共に進化してきました。
どの家庭にも、電気やガスが引かれ、明るく、音があり、夜間でも日中のような状態を作り上げることが可能になりました。
しかも、真っ暗闇の中であっても、パソコンやTV、スマホなどは、見にくいことが一切なく普通に映像を見たり話をしたりできるようになっています。
これによって、昔は、暗くなったら、自動的に副交感神経が活動し速やかに入眠で来ていたのですが、近代化が進むたびに、夜間も交感神経を活動することが多い生活になり、その様な環境を誰もが求めるようになっているのです。
その結果、時間だから眠ろうとしても、なかなか入眠できなくなってしまっているわけです。
7.ストレスが入眠障害の原因

入眠障害の原因として筆頭になるのがストレスではないでしょうか?
入眠障害だけでなく多くの睡眠障害の原因と言ってもいいでしょう。
けれど、何をもってストレスなのかというと、ストレスを感じていないのに、医師から「ストレスのせい」と言われてしまう事もあります。
これは、大抵の場合、食事や運動によるストレスだったりするのですが、話が長くなるのでここでは割愛します。
問題は、明らかに理解できている精神的なストレスが原因で、入眠障害となっている場合です。
ストレスと言って、
良い事なのか?
悪い事なのか?
は人それぞれ。
- 緊張やプレッシャー
- 嫌なこと
- やらなければならないこと
- 悲しい事
- ウキウキすること
- 大きな期待感
- 嬉しすぎること
これらは、すべて興奮状態を表し、交感神経を高めます。
よって、入眠の妨げになる感情ともいえるのです。
このような感情を落ち着かせる方法は、たくさんありますので、こちらも割愛し別の機会にお話しすることにします。
8.運動不足が入眠障害の原因

運動不足が原因となる人は、過去に
- 体育会系出身者
- 運動クラブ経験者
- スポーツ経験者
- 野山を走り回っていた幼少期
- 育った環境が起伏の激しい場所だった
など、一時的にでも、ほぼ毎日身体を使って生活していた人限定です。
限定と言っても、大半の人が入眠障害の原因となる可能性のある話になります。
少しでも運動に力を入れていた時代があると、かつて動かしていた筋肉が入眠障害の原因となることがあるのです。
それは、筋肉の特性によります。
筋肉の特性には、伸び縮みすると血液を流せるというものがあります。
血液を流すことで、新鮮な栄養素を取り込み、疲労物質を筋細胞から解放していくことが可能になります。
ところが、筋肉が動かないと、栄養が運ばれてこないのです。
いつまでも疲労物質がたまったままになってしまうのです。
そういうことから、疲れが溜まり、栄養を取れない筋肉は固くなってしまうのです。
筋肉が固まった状態を脳内では、【ストレス状態】と感知します。
このようなストレス状態はいわゆる緊張状態と同じようなものと捉えると理解できると思います。
緊張している時は筋肉が固まっていますよね?
この緊張状態が交感神経を高ぶらせ、入眠障害の原因となっているのです。
9.寝るための準備不足が入眠障害の原因

最後に、最も重要な話をしておきます。
睡眠には準備が必要です。
なぜなら、睡眠中には、
1)消化吸収
2)疲労回復
3)身体成長
4)脳内整理
5)糞便形成
と、仕事量がとても多いからです。
この仕事をすべて睡眠中に行う必要があるのです。
すべてが完了しないと、翌日にスッキリさわやかな目覚めを得られることはありません。
そのため、睡眠の邪魔になるようなことはできる限り、睡眠前に済ませておく必要があるわけです。
それが、
1)筋肉や関節を十分にほぐしておく
2)呼吸や心臓の拍動を抑えておく
3)脳内にある考え事や悩み事はすべて書き出しておく
最低限この3つは行っておく必要があるのです。
仕事から帰ってきて、シャワーを浴び入浴せず、食事を取ったら、スマホやPCで少し作業を済ませて、『さあ、寝よう』と思っても、筋肉を緩めることもしていませんし、目を使い、考え事も作ってしまっているので、入眠しにくくなるのが当たり前なのです。
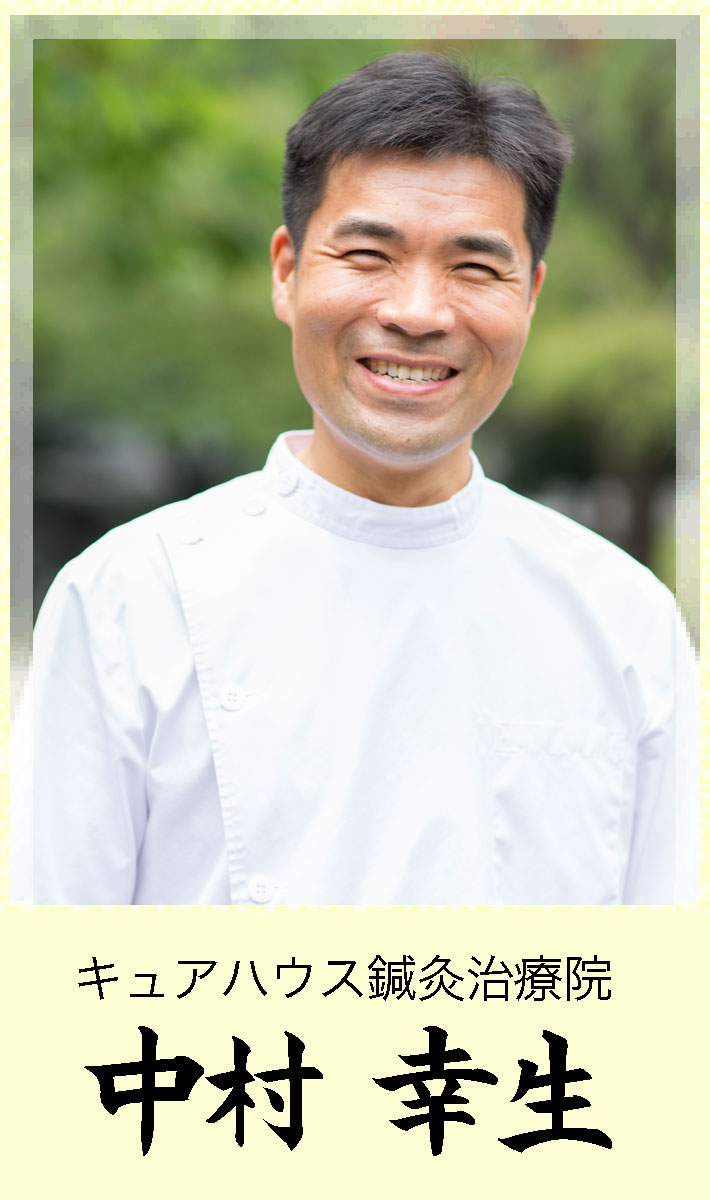
キュアハウス鍼灸治療院 院長。
病院に通うたびに、薬だけが増え、検査をしても『原因不明』と言われる痛みや症状を、ただ取り除くような治療ではなく、生活習慣を見直し、患者さん自身が自力で治すための手段を手に入れ、2度と同じような目に合わないような身体と習慣を身に着けられる治療と情報を提供。
これまで、20年以上に渡り、数々の治療院で経験を積み、施術の実績は80,000人以上。口コミが口コミを呼び、2016年のリピート率は98.7%。
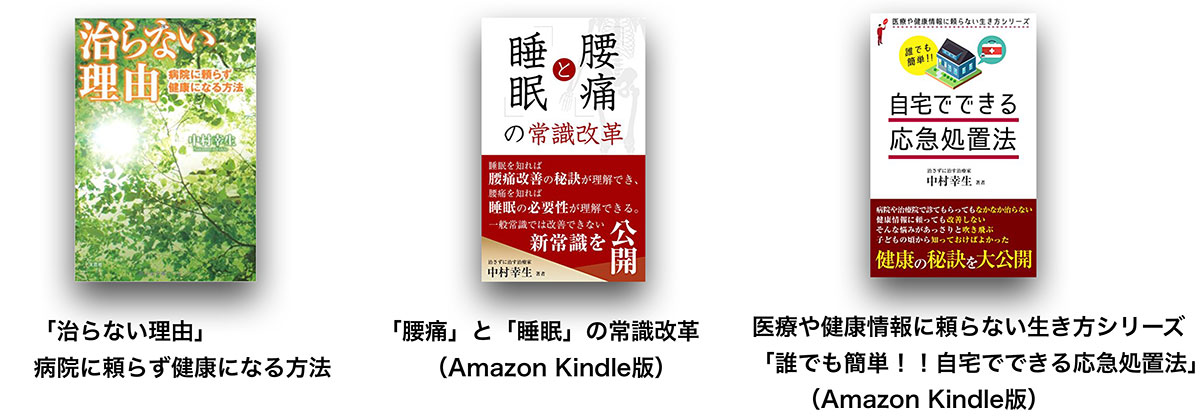
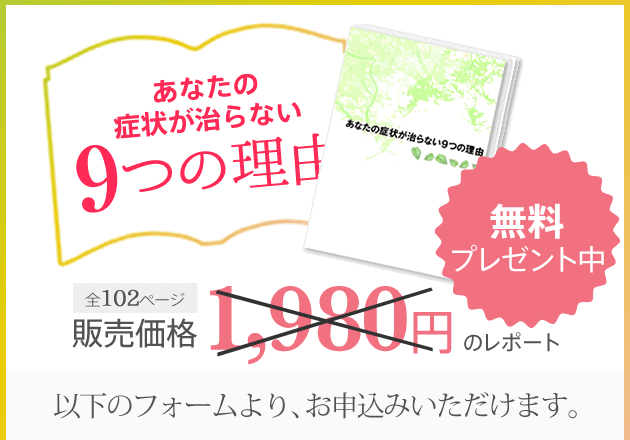


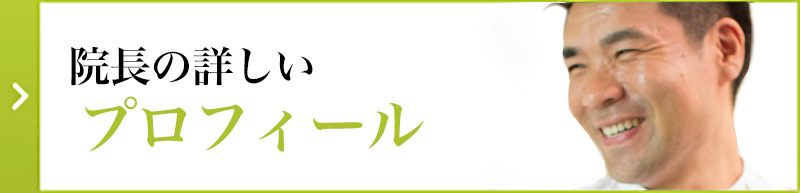
 0
0